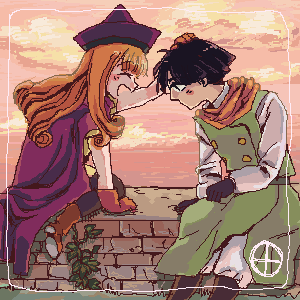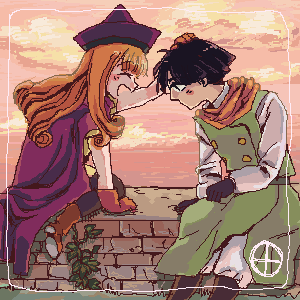
そりゃあ、敬愛する女(ひと)を自分の手で守りたいというのはどんな男性にもある考えでしょう。
私も例外ではありません。ありませんとも。
しかし私の場合、やや状況が違うのです。
まず私が神官というお役目を承った身分であること。
無駄な殺生は避けねばなりません。常に平等であらねばなりません。
全ての救いを求める人たちのためにお仕えするのであって、だれか一人に、というわけにも参りません。
まぁ、それは私が一国のお姫様のお目付け役であるということで、
だれよりも姫様を優先する名目は一応のところ立つわけです。
しかしもっともやっかいなある事実があります。
私の仕える長い栗毛のお姫様は、世界一腕っぷしの強い格闘家であることです。
そうなれば私が姫様を守るというよりも、情けないことですが、姫様の背の方に立っては、やれスクルトだ、やれザラキだとぶつぶつ呟いているだけのものになってしまうのです。
そんなことが、武道大会への道中にちくちくと痛み続けていたある日のことです。
「ひ、ひ、ひめさま!本当に、あの、登るんですか?」
「何いってんの、あったりまえでしょ!」
私にとっては「旅」でありましたが(あってほしいのですが)
姫様にとっては見知らぬ土地から土地へ行く「冒険」であるのです。
よって目的地でないにしろ、このような「冒険」を彷彿とさせる高い高い古びた塔などに行きあたれば、
通り過ぎるわけにはいかないようなのです。
まことに情けないことに、私はどうも、高いところは尋常でなく不得意であります。
しかし姫様には全く関係のないことで、
「しょうがないわね、足が動かないんだったら私が担いで上がりましょう」
などと常識を欠いた発言をなさるものですから、私は頭から血が一斉に引いていく音を聞いたような気がしました。
さらに、姫様はそんじょそこらの武道家とは比べるべくもないほど俊敏であり、
まあせっかちな性格であるとも言いますが、私が口をはさむ間もなくさらりと肩に担がれてしまい、
怒涛のスピードで塔を駆け上がってしまったのでした。
肩の上で泣き叫ぶ私に、「年寄りは遠慮するでの」という薄情なブライ様の一言が耳をかすめました。
◆
「・・・・・」
「ごめんごめん、でも落とさなかったでしょ?大丈夫だったでしょ?」
落とされたらそれこそたまったものじゃありません。
私たちは50階以上はあると見える塔のてっぺんにたどりついていました。
ひらけていて見晴らしの良い最上階では、既に大きな夕日が落ちかかっているのがよく見えました。
「せめて、塔中の敵と戦う時は降ろしてほしかったですよ!
姫様がせいけんづきを打つとき、片手で持ち上げられていた私の恐怖がわかりますかっ!」
「はいはい。でも落ちなかったでしょ?」
結果がすべて、とでもいうように姫様は聞き流してしまい、満足そうに塔の淵に腰掛けていました。
そう、サントハイムのお城でも、こうやって姫様の行き過ぎた「やんちゃ」にお説教しているとき、
いつも姫様はにこにこと腰掛けて足をぶらぶらさせ、「でも、大丈夫だってでしょ?」なんて繰り返すのです。
そんなところが憎めないと思ってしまう、私ではお目付け役としては不適任なのかもしれません。
私は一つ深呼吸で、まだ落ち着かない心臓に冷たい空気を送ってやりました。
「ほんとうに・・怖かったです」
二つの意味で、怖かったのです。
高いところへの恐怖、そして塔の中で姫様に万が一があった時、自分が姫様を守り切れたかという恐怖でした。
この笑顔がいつ消えてしまうのではないかと思うと、胸が切り刻まれそうになります。
十字架を握り、二人が無事であったことに感謝の祈りをささげていると、
いつの間にか姫様は足を動かすのをやめ、真剣に私の顔を見つめていました。
「怖い思いをさせてごめんね、クリフト」
私が思いつめた顔でいたからでしょうか、稀にみる弱気な姫様に、私は氷柱を飲み込んだような痛みが走りました。
お目付け役の自分が、姫様を不安にさせてどうするというのでしょう。あわてて私は笑顔を顔に戻しました。
「いえ、大丈夫ですよ。魔物は切り抜けられましたし」
といっても、倒したのは姫様で、私はと言えば
姫様の肩の上で守られながらスクルトだの、ホイミだの言っていたにすぎませんが。
「クリフトの大丈夫はあてにならないわ」
「それを言うなら、姫様のだって」
そこでやっと、私の好きな姫様の笑顔が戻りました。
私の方も、無理やり取り繕ったものでない、安堵の微笑みが自然と浮かんでいました。
「ねえ、クリフト」
「なんですか?姫様」
呼ばれた私は、なんとか勇気を振り絞って塔の淵に近づき、
なるべく下界を見ないようにしながら姫様の隣に腰掛けました。
「この旅は長くなるって、私そう感じてるの」
夕焼けに照らされた姫様の栗毛がふわりと風に乗りました。
金の髪のように反射して光るそれに目を奪われ、私は姫様の顔をまっすぐに見ることができません。
「武道会に行ったら、旅は終わるんですよ?」
「そうかもしれない。でもそうじゃないかもしれないわ」
私には姫様の言葉がよくわかりませんでした。
ただ、この旅が終わってしまうことに私自身、戸惑いを感じていることにその時気づきました。
旅は終わる、自分の言葉がそのままぐさりと胸に刺さってきたのです。
「それでもし・・もっと危険なこと、この塔より怖いことに立ち向かわなくちゃならなくなった、その時は――」
姫様の瞳がきらっと一瞬光を増したのは、夕日のせいだけではないような気がしました。
ただ私は黙って聞いていました。私は――
「その時は私がクリフトを守ってあげる」
小さな温かな手が私の頭をなでました。
「姫様・・」
「だから大丈夫。ね?」
この小さな体に、いったいどれほどのパワーを秘めているのでしょう。
そしてそれは、肉体的な力だけには留まらないのでしょう。
姫様の内なる強さに、−−私は守られている。この小さな手から伝わってくる強いこころ、強い優しさに。
目の奥が熱くなってくるのをじっとこらえて、私は言葉をかみしめました。
「姫様、もったいなきお言葉、感謝します」
姫様は満足したのか、照れたように笑うと再び私の頭をくしゃくしゃになでました。
「うんうん、任せなさい!」
まったく頼もしい姫様であられます。
そしてお目付け役の私はどうでしょう、情けない、情けないばかり言って逃げるわけにはまいりません。
「姫様、ならば私は、姫様が「大丈夫」と安心して言えるように、全力で姫様の背中を支えるお役目を仰せつかってもよろしいですか?」
スカラ、バイキルト、ホイミ。私にできることはわずかだけれど。
「うん!お願いねクリフト」
私は姫様の笑顔を守る騎士になりましょう。
そして姫様はその笑顔で私におっしゃるのでしょう。
『大丈夫だったでしょ!』
了
ブラウザバックでお戻りください